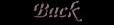Shadow Saga
Short Story9:side-Leonhard
「marionette」
一月ぶりに領地から皇宮に戻ってきた宮廷魔術師は、その若者を興味深く眺めた。
黒絹の髪と対極をなす、白磁の肌。黒曜石の瞳からは、あらゆる感情と表情が欠落しており、若者の美貌を、精巧な作り物めいて見せていた。実際、若者が瞬きも微かな身じろぎもしなければ、彼を美しい彫像だと思う者が居ても、おかしくないかもしれない。
若者の奇妙な生気の無さは、その額に嵌められた、禍々しい輝きを宿す黒金剛石の額環(サークレット)による、“制約(ギアス)”の呪いのせいだ、とフーリックは知っている。この呪いに囚われた者は、自我そのものを制約され、術者の忠実な操り人形と化す。しかし、若者の目の奥には、僅かな――ほんの僅かだが、強烈な理性の光が確かに灯されていた。
「凄まじいですな」
何が、という目的語を省略して、フーリックは口を開いた。
「これだけの異能は、1000年に1度も生まれるかどうかだ。容易には他者の意のままにはならんだろうよ。余にすらな」
グレゴール皇帝は、低く笑う。
「レオンハルト・ベルンシュタイン、18歳。フロレンツ王国メルファス地方フェラス村出身。生業は狩人……逸材とは、全く何処に埋もれているか分からんものだ」
「しかし、惜しむらくは」
唐突なフーリックの発言に、皇帝が豪奢な椅子を軽く軋ませた。
「ほう、何が惜しいと?」
「この者が女であれば、さぞや優れた陛下の御子を産んだでしょうに」
一拍の時を置き、皇帝は爆発するように笑い出した。
「異能とは血筋に現れるものではない――才もまた、血には宿らぬ。だが確かに、少なくとも、見てくれは素晴らしい子が生まれたやもしれん。まあ、見目が良い、というのも、一つの才ではあるか」
自分のことを話題にされているというのに、レオンハルトは皇帝の傍らに佇立したまま、周りのものを映してはいても見てはいない風の目を、動かしもしなかった。
絶望した者の目だ、とフーリックは思った。自分がどうして生きているのか、理由も目的も見失った者の目だ。それでいて、まだ光を見失っていない、意志の強い目。彼を、真の絶望に陥らせるには、何でもってその心を引き裂けばいいのだろうか。フーリックは、いずれは、この美しい若者が自分の目的に役に立つであろうと、内心に笑みを広めた。
フーリックの意図など知らぬげに、皇帝はレオンハルトに顔を向けた。
「“闇将軍(ダークジェネラル)”レオンハルト」
「は」
皇帝に呼ばわれ、レオンハルトは間髪入れずに応えを返す。皇帝のレオンハルトに対する支配は、完璧とはいえなくとも、充分以上であった。
「仮にも将軍と称される者が、軍を率いたことがない、などとは笑い話にもならん。この一月は、基礎の訓練に費やしたわけだが、この後はそろそろ実戦に出てもらう――しぶといフロレンツの残党との戦いに、な」
「陛下の御心のままに」
彼が初めて皇帝に会った時、皇帝を殺そうとまでしたと、今のレオンハルトを見て、誰が信じられるだろう。故国と戦え、と命じられてもあくまでも従順に、レオンハルトは深く皇帝に一礼した。
「一月で使えるようになるのですか、異能者というものは」
「だからこそ、価値がある」
疑う言葉の内容とは裏腹に、フーリックの口調は愉悦に満ちたものだった。皇帝もまた、同じように笑いを漏らす。ただレオンハルト一人だけが、相変わらず無表情のままでいた。
「ついては、お前に副官がつく。明日、その者に引き合わせよう。今日はもう下がってよい」
許可の形を借りた命令に、レオンハルトは無言のまま、フロレンツ王国式ではなく、ブルグント帝国式の敬礼をして、皇帝の執務室を退室した。生まれついてのブルグント人もかくや、というほどに板についた、見事な礼だった。
「副官をつけると」
興をそそられたように、フーリックは皇帝の発言をなぞった。
「あれは、単なる黒騎士などではなく、将軍だからな」
「異国人の、しかもあのようにまだ軍功もない、年若い将軍の下につくことをよしとする、さぞかし心の広い副官でしょうな」
「小人は度し易いが、それだけだ」
徹底して能力主義者である皇帝は、年齢を盾にして序列を決める方法を好まなかった。上の地位に行きたければ、それに相応しい能力を見せればいい。そうすれば、地位など自然についてくる。
ブルグント人でない、この宮廷魔術師がその地位を手に入れたように。
皇帝は、先ほどと別種の笑みを浮かべた。それは、何処か淫猥なものを連想させた。
「いずれにせよ、この場合は、“闇将軍”が若く美しい男であることの方が、問題が少ない」
「――女、ですか」
「しかも、“夜の女王”と呼ばれる高位魔族の女だ」
「それはそれは」
フーリックが破顔する。
「“夜の女王”は、若い男の精を糧とする一方で、非常に選り好みの激しい美食家であると聞きます。あれほどの美形の若者ならば、さぞかし気に入られるでしょうが……“制約”に縛られた人間相手では、如何ともし難いでしょうな」
「どう御するか、見ものであろう?」
皇帝は、呪いの奥底でもがく美しい若者の自我を見透かすし、更に縛り付けるかのように、眼を細めた。
レオンハルトよ、この先は同胞の血でその手を汚す、修羅の道だ。お前は、もう、逃れることが出来ない。その類稀なる異能者の力を存分に揮うがいい、余のために!
レオンハルトに与えられた居室は、皇宮の西塔最上階にあった。皇帝が起居し、執務を行う中央宮とは一本の回廊のみで繋がれており、従って、移動に際してはそこを通らねばならない。
その回廊の端、レオンハルトの進路に、誰かが立っている。
柔らかい輪郭から、立っているのは女と知れたが、レオンハルトはそこに誰もいないかのように、女を無視して歩を進めようとした。
しかし、女は大きく腕を広げ、レオンハルトを抱きとめる風にして、彼の歩みを遮った。のみならず、己の豊満な肢体を誇らしげに男の胸に押し付ける。
「あなたが“闇将軍”?」
血赤を思わせる色の唇が、妖艶な声を紡ぎ出した。レオンハルトは、無造作に女の手を払った。
「誰だ」
「皇帝陛下からお聞きになってないかしら」
ようやく、レオンハルトはまともに女を見た。
膝まで届こうかというほどに、長い黒髪。鮮紅色の瞳に、血の気が通ってないのかと思うほど白い肌。過剰なまでに色香を発散させ、男を狂わせようとする魔性の美貌は、背に折りたたまれた蝙蝠のものに似た翼を見るまでもなく、魔族の女だ。胸元には、何か不気味な紋様が描かれている。いや、描かれている、というよりは、肌の下を流れる血管が、自然とそのような形を作っているようだ。
「副官には明日、引き合わせると陛下は仰せられた」
「自分の上官になるという男を、先に見ておきたいと思ったのよ。いけない?」
冷たい、というには、何も込められたものがない眼で、レオンハルトは女を一瞥したが、それきり、やはりそこに誰もいないという態度を取り戻し、回廊を抜けて塔の中に入っていった。女は興味深そうな顔つきで、レオンハルトのすぐ後ろを追って、彼の部屋の中まで入り込んでいった。
レオンハルトがマントを留めていた飾りピンを外し、肩から下ろすと、さも当然のように女は甲斐甲斐しい動作でそれを受け取り、丁寧に畳んで壁にかけた。
いつもなら、楽な部屋着に着替えるところだが、女が自分を凝視している中ではそんな気になれず、襟元だけを緩め、レオンハルトは安楽椅子に身を沈めた。
「用がないのなら、出て行ってもらおうか」
飽きもせずに自分を眺め回している女に、レオンハルトはややうんざりした声で言った。意志や感情を“制約”されているとはいえ、それらが抹消されてしまっているわけではないのだ。
「それは命令?」
艶冶な笑みで女は首を傾げるが、レオンハルトの態度は変わらなかった。
「お前が俺の副官だというのなら、そうなる」
「残念ながら、私があなたの副官になるのは、明日以降。今はまだ、ただの男と女、よ」
「……」
「だから、用ならあるわよ」
レオンハルトは、女の言わんとしていることが分からない子供であれば良かったが、と、ちらりと思った。面倒な、と女から目を背けた。
女は、レオンハルトの脚の間を膝で割り、彼の上にのしかかるような姿勢を作る。レオンハルトの喉元から鎖骨、胸元へと指を滑らせると、一見華奢にも見える身体に、引き締められ、絞られた筋肉がしっかりとついている感触が伝わってくる。
皇帝には、必ず気に入るだろう、と言われたが、予想以上だった。顔もいい、身体もいい、声には少し、年頃の男らしい覇気が足りない気はしたが、それは自我を“制約”されているため、仕方ない。声質自体は申し分ない。
さぞや、いい味がするだろう。
「佳い男ね、あなた」
うっとりした様子で、女は引き結ばれたレオンハルトの唇に、自分の唇を重ねた。口腔に舌を差し入れられても、レオンハルトは無反応だった。
「そこまでにしておけ」
その唇と舌が首筋を伝い、服の中にまで手が潜り込み、肌を直接まさぐってきたところで、ようやくレオンハルトは反応した。しかしそれは、女が期待した反応とは違い、ひどく冷淡なものだった。女の体を突き飛ばすようにして立ち上がり、はだけられた胸元を直す。
「俺がお前に興味を持つとすれば、副官として有能かどうか、それだけだ。女として有能かどうかなど、興味はない」
「あら、私は興味があるわ。あなたが、上官として有能かも、男として有能かも」
「別に俺は、お前にとって男として無能でも構わん」
傲然と言い放ったレオンハルトの脳裏を、一瞬、金の髪を持つ娘の面影がかすめる。
黄金の糸をなびかせ、青い瞳で笑う娘は、たちまちのうちに闇の中に塗り潰された。その娘を確かに愛していた、という感情は、不自然な紗をかけられて、他人のもののように漠然として遠かった。
「不能なの? ひょっとして、まだ童貞?」
男が女に言われて、恐らくは最も屈辱的な単語を浴びせられても、レオンハルトは動じない。
「お前は俺の趣味と合わない。それ以上に理由が必要か?」
「まあ……面白いけれど、つまらない男!」
女は大仰に肩を竦める。胸にも脚にも大胆にスリットが入れられた服の切れ目から、豊かな胸の谷間やふるいつきたくなるような太腿が零れ出ているが、目の前の男は毛筋の先ほども、心を動かされた様子はなかった。
たとえ、“制約”にあらゆる感情を抑えられているとしても、意志とは別の、欲望までは普通はそうはいかないものを。それは、この美貌の若者が、恐るべき鋼鉄の意志の持ち主である、という証左ではないか。
将軍という称号を与えられた、皇帝の人形。果たして、単なる操り人形で終わるのだろうか、この男は。人形めいた美貌の深く、深い底に、己の意志を秘めた男。
「ならばお前は、男を溺れさせる以外に何か役に立つのか」
「それは明日以降お見せしましょう、“闇将軍”閣下」
女にとって、人間の男など、餌同然の意味しか持たなかった。魔界の万魔殿(パンデモニウム)から契約をもって人間界に召喚された時は、せいぜい契約の範囲で面白おかしく過ごそうかと思っていたが、どうやらずっと楽しいことになりそうな、そんな予感がした。
精を貪るよりも、もっと素晴らしい法悦を、“闇将軍”は経験させてくれるかもしれない。
「私は“夜の女王”、リーリエアと申します。魔界9大貴族の一人ですわ」
「貴族? お前が?」
初めて、レオンハルトの表情が興味を持った風に動いた。
「ええ。先ほどから見えますでしょう、この印……この“血の刻印”こそ、高位魔族の証ですのよ。この印は、魔王とその直接の血族以外は、貴族にしか持ちえませんの」
リーリエアが胸元を指す指先の動きを、レオンハルトは黒曜石色の目で追い、ようやく笑いに近いものを、唇に刻んだ。
「ならば、期待はさせてもらおう」
「ええ、どうぞご期待くださいな。それでは、どうもお邪魔いたしました。ごゆるりとお休み下さいまし。また明日、お会いしましょう」
先ほどまでの媚態はすっかり消え失せ、貴族、と呼ぶに相応しい気品を見せて、リーリエアは優雅に軽く膝を折る礼をした。
英雄詩(サーガ)では、“闇将軍”は、“不屈の剣士”に倒され、“美しき娘”が、帝国に囚われていた兄、“静かなる魔法戦士”を救い出した、と高らかに謳う。
レオンハルトは、フリードリヒ達の生存を知らぬまま、絶望の糸に絡め取られ、皇帝の操り人形“闇将軍”として、戦いに身を投じようとしていた。それが後の自分に、どれだけの更なる絶望をもたらすか、今の彼には知る由もなかった。

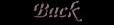
Copyright (C) 2006 Ryuki Kouno.