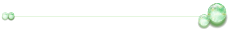Shadow Saga
Short Story5:side-Leonhard
「hope」
大きくなったら、何になりたい?
俺達がほんの子供の頃、大人たちは時々、そんな事を訊いた。まだ世間も何も知らない子供の俺達は、無邪気に色んな答えを返したもんだ。お姫様になりたいとか、魔法使いになりたいとか、騎士になりたいとか。大方は、大人が読み聞かせてくれた物語なんかに出てくる、主人公になりたがったもんだ。
今から考えたら、自給自足で生きていた、ほんの小さな村に生まれた子供が、そんなものになれるわけがないのにな。もっとも、今だからこれも分かるが、そんなことを訊いた大人たちも、かつてはそんな夢を抱いていたんだろう。日々の生活の中で、夢や希望は擦り切れて、忘れていくもんだけど、消えてなくなるわけじゃなくて、それで、大人はふっと自分の子供時代を思い出して懐かしんで、自分の子供に問いかけるのかもしれないな。だからか、子供がどんな突拍子もない夢を語っても、大人たちは否定もせず、にこにこしてそれを聞いてた。
……もっとも「ここで平穏無事に暮らせていけたら、それでいい」とか答えた、可愛くない子供もいたわけだが。
そうなんだよなあ。俺達が生まれたフェラス村は、住民全員が知り合い、どころか、よその家で飼ってる牛や羊や鶏や犬や猫なんかとも、皆知り合いの本当に小さな村でさ。今はもう、地図にもないけどな。無くなったから。それはともかくとして、そんな村に、あいつは、レオンハルトのヤツは、子供の頃から外に出る夢も見ずに、平穏無事に暮らせていけたら、ときたもんだ。あれは……あいつ、12歳くらいの頃に言ったんだったかな。子供が言うことかよ、あれ。
レオンハルトは、俺達同世代の、村の子供の中の最年長で、実の妹のユリアナに対してだけではなく、皆の「兄さん」だった。そのせいかどうか、レオンハルトは、おおよそ子供らしくない子供で、ずっと大人に近かった。俺は、あいつが子供っぽい我儘を言ったり、駄々をこねたり、泣き喚いたりするのを、見たことも聞いたこともない。ユリアナにも聞いてみたが、ユリアナもそんなレオンハルトは知らない、と言っていた。無理してたとかそんなんじゃなく、ありゃただの生まれつきの性格だったんだな、きっと。我欲が薄いっていう。
どっか浮世離れしてた、レオンハルトは。それこそ、本当は、どっかの王侯貴族の家に生まれるはずが、間違ってド田舎の村に生まれてきたんじゃないのか、ってくらいに綺麗な顔立ちをしてて。何をさせても飲み込みが早くて、上手にこなして。御伽噺に出てくる王子様って、レオンハルトみたいな人じゃないのか、みたいなことを思ったこともある。
ただし、この王子様、御伽噺に出てくるためには、ちょっと欠けてるものがあった。
王子様と対になる、愛を捧げるべきお姫様。
まあ、何だ。ぶっちゃけ、あいつ、もてたんだよなあ。ちょっと分けてくれ、と言いたくなるぐらいに。
そりゃそうだろう、レオンハルト、背は高いし、礼儀正しくて優しいし、細身に見えるけどちゃんと筋肉のついた、鍛えられた身体つきだし、何と言ってもあの顔だ。気品があって、男の俺でも時々見とれるぐらいに、いっそ常識はずれなくらいに整った綺麗な顔。俺は、レオンハルトの一番親しい友人だったから、あいつへの仲介もよく頼まれたっけ。一度や二度じゃきかなかった。ああ、そうだよ、どうせ俺は「いい人」だろうよ。レオンハルトと比べたら、誰だってそうなるっての。つうか、あいつと比べられるって事自体が理不尽だ。
でも、何時だってあいつは、ちょっと困ったように「ごめん」って断ってた。あの王子様は、お姫様を探してなかったのかもしれない。興味無かったんだろうな。俺らがあの娘が可愛い、あの娘が美人だ、なんて話をしてても、あいつ、全然乗ってこなかったし。
そうこうしているうちに、レオンハルトは学校を卒業して、名実共に、一足先に子供から大人になった。始めは、狩りの師匠である、父親と一緒に森に入ってたレオンハルトだったが、一人前の狩人になるのに、一年も掛からなかった。
俺はレオンハルトよりも一こ年下で、それはつまり、俺ももうすぐ学校を卒業して、大人の仲間入りをするってわけで。
それがどうにも俺には億劫だった。
別に、ずっと子供でいたいとか、そんなんじゃなかったけど。いや、やっぱり俺は子供だったんだと思う。何となく、その時の俺は家に帰る気がしなくて、小川沿いの道を、行く宛ても無くぶらぶらしていた。
「どうした、フリードリヒ?」
すると、向こうからレオンハルトが、こっちに向かって歩いてきているところに出くわした。手に鍋を持っていることから察するに、うちに夕食を差し入れてくれる途中だったんだろう。俺のオヤジは所謂男やもめで、一人っ子の俺との、男所帯の俺ん家、こうしてレオンハルトとか、彼の母さんとかに面倒見てもらわないと、飯も食えない情けない現実。
オヤジ、鍛冶屋としての腕はいいんだろうが、職人気質っていうか、寝食を忘れる、なんてのもざらでさ。オヤジは良くても、育ち盛りの俺には辛いって。背、伸びなくなったらどうするんだよ。そうじゃなくても、長身のレオンハルトとはもう結構な差がついてて、話す時、見上げなくちゃなんないから、時々首が痛いんだ。カールは、もうありゃ熊並なんで論外。
「何だか浮かない顔だな。腹でも減ってるのか?」
「……確かに、ちょっと腹は減ってるけどな」
そんなに浮かない顔してたんだろうか、俺。ていうかレオンハルトよ、俺が浮かない顔をしてるのは、腹が減ってる時なのかよ!
「少し食うか?」
そう言って、レオンハルトが手に持った鍋の蓋を開けた。シチューのいい匂いが、鼻腔を刺激する。すげえ美味そうだ……料理上手いんだよな、レオンハルト。はっきり言って、妹のユリアナよりも上手い。
「や、そうじゃなくてレオンハルト。……なあ、ちょっと、話、聞いてくれるか?」
と言いながら、俺はさっさと小川の川岸に腰を下ろした。レオンハルトが、否というわけがないのを、俺は分かってるから。やっぱり、レオンハルトは特に困った風も無く、俺に倣うように隣に座った。
「お前さあ、今の生活に満足?」
俺の言葉に、レオンハルトは澄んだ黒曜石色の目を、少し驚いたように俺に向けた。
「どうしたんだ、急に? お前は何か不満があるのか?」
「ん――別に、不満ってわけじゃないんだけどさ……」
その辺に落ちていた小石を、手遊びに川に投げ入れると、ぼちゃんと音を立てて沈む。川面が、波紋でゆらゆら揺れた。意味もなくそれを眺めて、一旦口ごもった俺は再び口を開いた。
「何かさ、俺、このままでいいのかなーって。不安、なのかな。このまま、オヤジの後継いで鍛冶屋になってさ」
「お前、鍛冶屋になるのが嫌なのか?」
柔らかい声音で、レオンハルトが訊く。優しい顔で、微笑んで。
「嫌なんじゃないんだけどさ……ええと、そのさ、笑うなよ?」
「笑わないよ」
「馬鹿にすんなよ?」
「しない」
しつこく念を押す俺。このやり取りこそが、正に大人と子供だよな、とは思うけど。自分が子供じみてることは分かってて、俺は誰にも言ったことのない、でもずっと抱いていた夢を、レオンハルトに告げた。
「俺な……本当は、剣士に、なりたいんだ」
俺の祖父さんは、西方大陸の出身だったそうだ。その血を濃く引いた俺は、黒髪やブルネットの多いこの北方大陸の人間にしては珍しく、薄い亜麻色の髪をしてて、目の色も黒とか茶色とかじゃなくて、鮮やかな緑色だ。で、その祖父さんは、西方大陸から北方大陸に渡ってきて、大陸をあちこち放浪した末に、この村に落ち着いて祖母ちゃんと結婚した、って聞いてる。
俺は、祖父さんに剣を習った。祖父さんに、色んな土地の話を聞いた。祖父さんの話は面白くて、俺に、この村から出て、もっともっと広い世界を見てみたい、なんて、見たことのない外の世界への憧れを抱かせるには充分過ぎるほどだった。そして、鋼を打つよりも、剣を振るう方がよっぽど楽しかった。
けど、もうすぐ、夢見る時間は終わる。
ウチは、村でただ一件の鍛冶屋だ。鍛冶屋がいないと、村がどんなに困るか、よく分かってる。
それでも、現実離れした夢を捨てられない俺は、どうしようもなく子供だ。
「捨てる必要なんて、ないだろう」
声に出した覚えもないのに、レオンハルトは俺の内心を見透かしたように、そう言った。俺はぎょっとして、そのせいで思わずバランスを崩して小川に落っこちるかと思った。
「おいおい、危ないな」
すぐに俺の手を掴んで、レオンハルトが俺の姿勢を立て直してくれた。でも、俺がびっくりしたのは、お前のせいだぞ、レオンハルト。
「……何で俺の考えてること、分かった?」
俺が、探るようにそう言うと、何でもないことのように、あっさりとレオンハルトは答える。
「分かるな、と言う方が無理だろう。お前は考えてることが、逐一、顔に出るからな」
そ、そうか? そうなのか……? 俺、そんなに顔に出やすいか?
俺は、困惑して自分の顔を撫でてみたりした。
「ほら、そんな風に」
くつくつ、と喉の奥でレオンハルトが笑い声を立てる。ちょっとむっとくるなあ、おい。
「笑うなよ!」
「最初に、お前が笑うなと言ったことで、笑ったんじゃないだろ」
そりゃそうだけどさ。
「捨てるのは簡単だが、それを拾い上げることは難しい――それに、仮に拾えたとしても、拾い上げたものが、捨てたものと同じものとは限らない。だから、捨てたくない」
急に、レオンハルトがそんなことを言い出したので、俺は目をぱちくりさせた。
が、次にレオンハルトが口に出した言葉に、俺は小川に落ちるどころじゃなく、あんまりの衝撃に凍りつく羽目になった。
「……俺の好きな女が、そう言ってた。俺もその通りだと思う」
……えーと? 俺の耳はちゃんとついてるよな? 俺の耳はちゃんと、聞こえてるよな? 俺の頭、変になったんじゃないよな?
何て言いました、レオンハルトさん?
……「好きな女」……?
「おおおおおおおお前、レオンハルトお前! す、好きな女がいたのかっ!?」
馬鹿みたいに声が上ずった。でも、しょうがないだろ。これが青天の霹靂じゃなくて、何なんだ!
だって、この孤高の王子様がだ! 誰も知らない間に、お姫様を見つけてたんだぜ!? 驚くなっていう方が無理だって!! ああもう、やってくれるったらありゃしねえ!
「ああ」
俺が滑稽なほどに取り乱しても、レオンハルトは全くの平静。
「誰だよ、その女! 何処の子だ!?」
「ここの娘じゃない」
そりゃそうだろうよ。この村の娘だったら、絶対、噂になってるに決まってる。皆が知り合いの小さい村なんだからな、それこそ。
「お前の知らない娘」
俺の知らない娘? 一体何処でそんな子と知り合ったってんだ、何時の間に!
「ユリアナも知らないのかよ?」
「誰も知らない娘」
「何だよそれ! 何処の誰だよ、いいじゃねえか俺とお前の仲だろ、勿体つけないで教えろよ!」
レオンハルトが、ちょっと困ったように笑う。
「いずれ、な。今はまだ……言えない」
秘密のお城に隠した、秘密の恋人かよ。ああ、ますます王子様じみて。それがめちゃめちゃ板についてるってどうよ?
が、何か、こういう、男と男の会話、みたいの、レオンハルトとするのは新鮮だ。したことないからな。ついでだ、訊いてやれ。
「美人か?」
「美人だ」
「ヤッた?」
しょうがないだろ、俺だって年頃の男子なんだから。そういう好奇心が働くの、普通だろうが。悪いかよ!
「それ以上は秘密だ」
顔色も変えずに、レオンハルトは言った。
「あ、そう、つまりもうヤッたわけね……ああ畜生、これだけはレオンハルトに勝てると思ってたのにな!!」
ごろり、と俺がその場に仰向けにひっくり返ると、レオンハルトが不本意そうに俺を見下ろした。
「おい、勝手に決め付けるな、フリードリヒ」
「あのな、レオンハルトは俺のこと凄く分かりやすいっていうけど、俺に言わせりゃレオンハルトだって分かりやすいぜ。お前、嘘つきたくないとき、絶対にはぐらかそうとするだろ」
「……」
珍しく、レオンハルトが反論できないってことは、自覚はあるってことか。うわ、何か気持ちいいなこういうの。いつもは頭の上がらない相手に、一杯食わせた、って感じ?
「ユリアナに」
「あん?」
「お前はそんなに早く手を出すつもりだったのか?」
だが、反撃はより強烈だった。俺はぶっと吹き出して、次に激しく噎せ返った。ごろごろ転がりながら咳き込む。めちゃくちゃ苦しいぞ、おい!
「な、な、何を言い出すんだよ! そこで何でユリアナが出てくんだ!」
苦しい咳がようやくおさまると、俺はレオンハルトに食ってかかる。
「俺としては、お前がユリアナを好きじゃない、と言う方が驚きなんだが」
それも俺が分かりやすいってのかよ!
……ユリアナは、可愛いと思うさ、そりゃ。兄貴のレオンハルトは綺麗な顔立ちだが、ユリアナは可愛いって感じだ。黒い癖っ毛がふわふわしててさ。でもって、あいつ、最近、急に女らしくなってきたんだよなあ。胸、結構でかいし。
……じゃなくて!
俺は、そんなにレオンハルトに気取られるほど、分かりやすい目でユリアナを見てたってのか!?
「フリードリヒ」
「あんだよ」
レオンハルトに答える声が多少、不貞腐れたものになるのは仕方がないだろう、この際。
「ユリアナに振られるなよ」
「大きなお世話だよ!」
「ユリアナも、夢を見てないお前なんか嫌だろうからな」
「え?」
俺は多分、その時、結構な間抜け面だったと思う。その俺の面が可笑しかったのか、レオンハルトは声を立てて笑った。そのレオンハルトの笑顔は、――本当に、幸せそうだった。
◇ ◇ ◇ ◇
人生、何がどうなるか全くもって分からない。
俺の夢は叶った。それどころか、俺は「聖なる剣を操る逞しき不屈の剣士」なんて英雄詩(サーガ)に謳われる勇者にまでなっちまった。
勿論、それと引き換えに失ったものは決して小さくなかったし、俺が勇者になったのは、俺一人の力だったわけじゃない。……それでも、今の俺は、胸を張って言える。俺は今、物凄く幸せだと。
そうだろ? 俺は、憧れてた剣士になって、国を救った勇者になって、近衛騎士団長に迎えられて、好きな女と結婚して――。これが幸せでなくて、何だって言うんだ。
なあ、レオンハルト。お前、今、どうしてる? お前はまだ、自分を忌み、憎んでいるのか?
ユリアナにも、俺にも、別れの言葉すら告げずに、何処かへ行ってしまったお前。
誰よりも愛していた恋人を失い、闇の力に操られて、望まぬまま罪無き多くの人々の血で、その手を染めたレオンハルト。お前の願いは、お前の望みは、何一つ叶わなかった。失うばかりで、何も手に入らなかった。レオンハルトは異能者で、人智を越えたような力をあいつは手に入れ、いや違うな、体の中に眠っていた力を目覚めさせられたけど、それも、あいつはそんなもの、望んじゃいなかった。
あいつが、最後に口にした、望みらしきものは「殺せ」という一言だった。あんなに優しかった黒曜石色の目は、自分への侮蔑に凍り付いてしまっていた。
レオンハルト、お前は夢も希望も捨ててしまったのか? もう二度と拾えないことを承知で、捨ててしまったのか?
なあ、レオンハルト。俺もユリアナもカールも、お前が不幸になることなんて、望んでないんだ。お前が俺達の幸せを、願ってくれるように、俺達だって、お前に幸せになって欲しいんだよ。自分にはそんな資格は無いなんて言うなよ。何か、自分のために何か願ってくれよ、レオンハルト。
誰が何を言おうと、お前は「剣と魔法を意のままにする静かなる魔法戦士」、俺達のかけがえのない大切な仲間。
だから、少しでもいい。願ってくれ、夢を見てくれ、無理だなんて言うな。俺に捨てるなと言ったのは、お前じゃないか。幸せだった頃を、知ってるだろ? 覚えてるだろ?
――生きてるんだから、少しでも、幸せに生きてくれ。本当は、俺よりもお前は不器用だと思う、生き方が。だからこそ、幸せになって欲しいと、願わずにいられないんだ。
何処か遠くにいる友よ。
どうか。

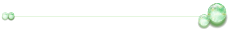

Copyright (C) 2004 Ryuki Kouno.