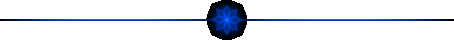Shadow Saga
Short Story3:side-Leonhard
「Forget-you-not」
その花の色は、彼女の瞳の色に似ている。
いつも、俺に微笑みかけてくれていた、あの青い瞳に。
「私を忘れないで」という名の、その、花は。
◆ ◆ ◆ ◆
旅をしていると、日が落ちる前に、都合よく旅籠に辿り着けるとは限らない。大体、目的はあれども、その目的地が判然としない旅であるのだから、当然といえば当然のことかもしれない。
初夏のこの季節、日は長いといっても、やはり暮れて夜が来る。その日の行程はそこで止めて、レオンハルトとカインは、野宿の準備を始めた。
もっとも、準備とは言うが、カインは実は所謂「生活能力」は皆無に等しい。過去の記憶を失っているから、というだけではない。その、カイン・H・ハーバート・アーヴィノーグ、などという家名を誇るような長い名前や、美しい高価そうな宝飾品を身に着けていたこと、規律に慣れたらしい身ごなしなどからして、レオンハルトは、カインを貴族出身ではないか、と推測しているが、それを証明した形である。身分の高い貴族の若君が、自分で自分の面倒をみる、などとありえない。
そういうわけで、いつも、レオンハルトが魔法を使って火をおこし、食事の支度をして、後片付けまで全部する。しかも、レオンハルトが携行食を利用して作る食事が、また旨い。そんなわけで、カイン自身もそれには引け目を感じている、というかレオンハルトに申し訳ない、と恐縮する気分があるようだった。しかし、出来ないものは出来ないもので仕方ない。そんなわけで、結局はレオンハルトの世話になりっぱなしのカインだった。堅い地面の上で寝るのがさほど苦痛でないことが、せめてもの救いだろうか。
麗しの森と湖の国、と称されるフロレンツ王国は、美しい緑の森と碧い湖を国土に多く擁する。また、その湖から発する川も少なくない。
水の綺麗な小川の傍に、夜の褥(しとね)を定めると、レオンハルトは食事の準備のための水を汲み上げようとして、気付いた。
川岸で、ひっそりと小さな花を咲かせた青色の群れに。
(……勿忘草)
慎ましやかな五つの花弁を持つ花に触れると、鮮やかに、レオンハルトの耳に甦ってくる声があった。
「ねえ、レオンハルト。この花の名前、何ていうの?」
新雪を思わせる白い肌、黄金を糸に紡いだような髪、薔薇の花びらに似た唇、貴石の輝きを持った青い瞳の娘は、とても美しい。しかし、レオンハルトが彼女に惹かれたのは、その美しさのため、だけではなかった。
常にしっかりと前を向いて、好奇心に輝く瞳が。心から楽しそうに、嬉しそうに笑う青い瞳が。何よりも、愛しかった。誰よりも、愛している。
初めて二人が出会った、森の中の泉。その水辺に咲いていた、彼女の瞳の色に似た可憐な青い花を、ほっそりとした指が差していた。レオンハルトも、男なのに細い手だ、とよく言われるが、彼女の手は、それよりももっと細かった。
「勿忘草、だよ。アルテミシア」
しゃがみこんだ恋人の隣に、レオンハルトも腰を下ろした。
「私を忘れないで、って名前なのね。ちょっとロマンチックだけど、何か由来があるのかしら」
「ああ……伝説があるんだ。昔、恋人のために水辺の崖に咲いていた、この花を摘もうとした騎士が、足を滑らせて、川に落ちて流された。彼が花を恋人に投げて叫んだ、最期の言葉――『私を忘れないで』、それが花の名の由来、だそうだ。それ以来、“真実の愛”を示し、『恋人達の花』とも呼ばれている。地方によっては、この花を恋人に贈る習慣もあるらしい」
「あら」
少し悪戯っぽく微笑んで、アルテミシアはレオンハルトの腕に、自分の腕を絡めた。
「ロマンチックというか……、恋人の花としては、ちょっと不吉ね。謂れが」
「不吉?」
「だって、そうでしょう? その騎士は、花を摘もうとして、命を落としたんだもの。花に罪は無いけど、でも、やっぱり、あんまり幸せじゃないわよね、それが恋人達の花の由来というなら。私は、貴方にはこの花を贈って欲しくないな。そんな伝説とか関係なく、こうやって、ひっそりと咲いてる方が、花にとっても幸せじゃないかしら」
そう言って、アルテミシアは甘えるように、レオンハルトの肩に頬を凭れかけさせる。細身のレオンハルトだが、その肩は意外に広い。
「もしも」
柔らかい木漏れ日が、長い金糸の髪を煌かせていた。
太陽の光を、そのまま髪にしたような黄金色に輝く彼女の髪の色は、夜の闇の色をしたレオンハルトの黒い髪とは対照的だった。アルテミシアは、レオンハルトの光を弾く艶やかな黒髪を、「星空みたいね」と言って少し羨ましがった。
「私が、その騎士の立場だったら、『私を忘れないで』とは言わないわ」
「アルテミシア」
「おかしいと思う?」
「さあ、分からないな。君に、忘れないで、と言われなくても、俺は忘れないだろうから」
「違うの、レオンハルト。私は、そうなったら、私のことを忘れて欲しいのよ」
「え?」
戸惑った顔の恋人に、アルテミシアは軽やかな笑い声を立ててみせた。
美貌の上を様々な表情がよく転がる様は、万華鏡に似ている。そのどの表情もが、違う美しさを持つというのも、万華鏡と同じだった。
「どっちにしても、私は忘れないけど」
「それは、何だかずるくないかな」
思わず、レオンハルトは苦笑してしまった。右腕はアルテミシアが掴まっているから、左手で、彼女の長い髪を一房、さらさらと指に流す。アルテミシアは心地良さそうに目を細めた。そのくせ、きっぱりとした声で言う。
「そうよ、女はずるいの。そして、逞しいの。愛する人を悲しませるくらいなら、忘れ去られた方がずっといいのよ」
娘の白い頬が、綻んだ。
「けれど、そんなのはやっぱり嫌。私は――」
青い瞳が、黒曜石の瞳を、真っ直ぐに見上げる。
「貴方と、幸せになりたい」
「ああ」
静かに、レオンハルトはアルテミシアの背を抱き寄せた。しなやかな細い腕が、レオンハルトの背に回された。
「俺も、君と幸せになりたい」
そっと口づけを交わす恋人達を見守るように、水辺の青い花が微風に小さく揺れていた。
ずっと、一緒に居られると思っていた。
ずっと、一緒に居たいと思っていた。
けれども、まさか、本当にそんな日が来るなんて。
君を失う日が、来るなんて。
どうして、俺でなくて君が、炎の中に消えなければなかったのだろう?
花は相変わらず時期が来れば咲くけれど、その花の名前を俺に訊いた、君はもういない。
花の色と同じあの青い瞳は、もう俺に向けられることはない。
どんなに指を伸ばしても――君には、もう届かない。
忘れない、忘れない。忘れられない。
愛している。君を、君を、君を。
青い花と同じ色の瞳をした、君を忘れられない。
もう二度と、この腕に抱くことの出来ない君を、忘れない、愛している。
「私を忘れて」と言った君。
「私を忘れないで」という名の花と同じ色の青い瞳を持った君を、忘れない。
愛して、いる。
愛しているんだ、アルテミシア。
「……レオンハルト、どうかしたのか?」
――どうやら、レオンハルトは、自分で思った以上に長い間、丈の低い茎に群れ咲く、小さな青い花を見つめていたらしい。いつの間にか、焚き火に薪をくべていたカインが、傍まで歩み寄ってきていた。
レオンハルトの手元に、カインが視線を落とす。
「花、がどうか?」
何でもない、と誤魔化してしまうのは簡単だったが、レオンハルトはそうしなかった。レオンハルトにとってカインは、嘘も、誤魔化しも、必要としない相手だから。
「懐かしい、花だったんでな」
「……そうか」
レオンハルトの声音で、カインはレオンハルトの言う“懐かしさ”の意味を察したようだった。
「何ていう名前の花なんだ?」
「勿忘草、だ」
「私を忘れないで、か」
己の過去の記憶を失った青年は、秀麗な顔に、自嘲めいた表情を浮かべる。
「思わせぶりな名前だが、何か謂れがあるのか」
花の名前を聞いたカインの反応が、失った恋人のものと似ていたので、レオンハルトは小さく笑った。
「昔の伝説が、その名の謂れになっている。恋人のために、岸辺に咲くこの花を摘もうとした騎士が、足を滑らせ川に落ちて、流された。その際に、恋人に花を投げて、『私を忘れないで』と言った。その最期の言葉が、花の名前になったんだ。それ以来、『恋人達の花』とも呼ばれている」
レオンハルトの説明も、かつて恋人に話したものと、大して変わろう筈もなく。
「ロマンチックというか何というか、恋人の花としては、少し不吉な謂れだな」
そして、カインは肩を竦めて、また、アルテミシアと同じような感想を洩らした。
その時不意に、カインの横顔がひどく女性的に見えて、レオンハルトは驚いた。カインは、確かに恐ろしいほどの美貌の主だが、特に女顔ではないというのに。性別云々もあるが、そもそも、カインとアルテミシアでは、その身に纏う色彩からして違う。金の髪に青い瞳のアルテミシアに対して、カインはレオンハルトと同じ闇色の黒い髪と、光の強さや角度によって色が違って見える、不思議な黒紫色の瞳を持っている。あえて共通点を挙げるとすれば、人並みはずれて見目麗しい、ということぐらいだろう。
だが、レオンハルトはすぐに思い当たった。微かな苦笑の形を、唇が作る。
(……ああ、そうか)
無意識に、レオンハルトはアルテミシアの面影を、カインに重ねていたのだ。
私を忘れないで、という名前の青い花の伝説に対する、感懐が二人ともそっくりだったから。
レオンハルトは水を汲んだ皮袋を手にして、静かに立ち上がった。
「腹が減っただろう?」
唐突にそう言われて、カインは一瞬、彼らしからぬ子供じみた、ぽかんとした顔つきになったが、すぐに、
「ああ、割と、な」
と、笑った。その笑った顔が、またアルテミシアに重なって見えた。レオンハルトは、自分でもどうかしている、と思った。
(アルテミシア)
あの、勿忘草の花が。
その花の名が、その青い色が、殊更に、失った恋人を思い出させる。
私を忘れて、と彼女は言った。永遠の別離の際にも、私のことなんか忘れて、と言った。
(……忘れられないよ、アルテミシア)
青い花は、そんなレオンハルトの思いなど関係なく、ただたおやかに咲いていた。
◆ ◆ ◆ ◆
その花の色は、彼女の瞳の色に似ている。
いつも、俺に微笑みかけてくれていた、あの青い瞳に。
「私を忘れないで」という名の、その、花は。
その名の通り、彼女を思い出させる、青い小さな花。
勿忘草の花言葉は、「私を忘れないで」「真実の愛」「誠の愛」、そして――――「記憶」。
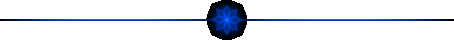

Copyright (C) 2003 Ryuki Kouno.